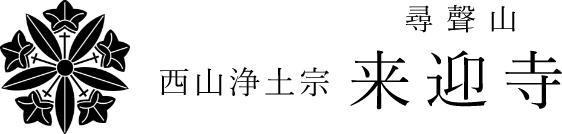来迎寺のはじまり
西山浄土宗 尋聲山 来迎寺は、室町時代の文亀元年(西暦1501年)大友氏 第18代の守護 大友親治公(親繁の5男)が勧請し、文忠梵榮上人により開山されました。開山依頼500年をこえて現在の地に守り続けられています。
当山が創建された時代背景は、大友氏が南北朝の動乱、それに続く大内氏との抗争、更にその間の一族による内輪もめは150年におよび、領内は疲弊し、領民は窮乏し、人々は救いを求めて坤吟していました。
親治の父、第15代親繁が漸く領国を纏めたものの、後継の第16代政親襯繁の長男)、第17代義右父子が相伐するという凶事で大友氏の危機となります。この時一族、家臣を統合して領国の再生に立ち上がっ たのが第18代親治でした。親治は年少の頃から文忠梵栄上人の薫陶を受けていた親治公は、文忠梵栄上人を開基とし、浄土宗の由緒ある寺号「来迎寺」をもって開山しました。当山はこのような大分の歴史上重要な時期に使命を担って創建されました。
元禄12年(西暦1699年)に戸倉貞則により著された「豊府聞書」には寛永16年(西暦1639年)府内藩主日根野吉明公が当来迎寺で肥後藩主細川忠利候をもてなしたと記されるほど「来迎寺は広大で美しく、書院は黄金の障壁画で飾られた見事なものだと記されています。
戦国時代にあっても「来迎寺」は壮麗な寺院であったと推測されます。


境内
-

本堂
昭和20年、空襲により焼失。昭和42年、再建。本堂には阿弥陀如来立像、観音菩薩、勢至菩薩。脇壇には善導大師 法然上人、西山上人、文忠梵榮上人を祀っています。
-

山門
山門は嘉永7年(1854)に再建されました。その「姿・形」さらに「建築部材」をはじめとして当時の来迎寺を支えた豊かさを目の当たりにできます。
-

梵鐘
梵鐘は文化10年(1813)に鋳造され、第二次世界大戦の中、「供出」という災禍に遭遇し佐世保の西蓮寺に納まっていました。返還交渉を重ね、昭和53年に無事帰ってきました。
-

観音堂
観音堂は江戸時代に安藤家より寄進されたと伝わっています。
交通アクセス
来迎寺の概要
| 山号 | 尋聲山 |
| 寺号 | 来迎寺 |
| 宗派 | 西山浄土宗 |
| 住職 | 第三十三世住職 槇島 隆幸 |
| 住所 | 〒870-0024 大分県大分市錦町1丁目1-30 |
| 電話番号 | 097-533-0611 |
| FAX番号 | 097-533-0617 |